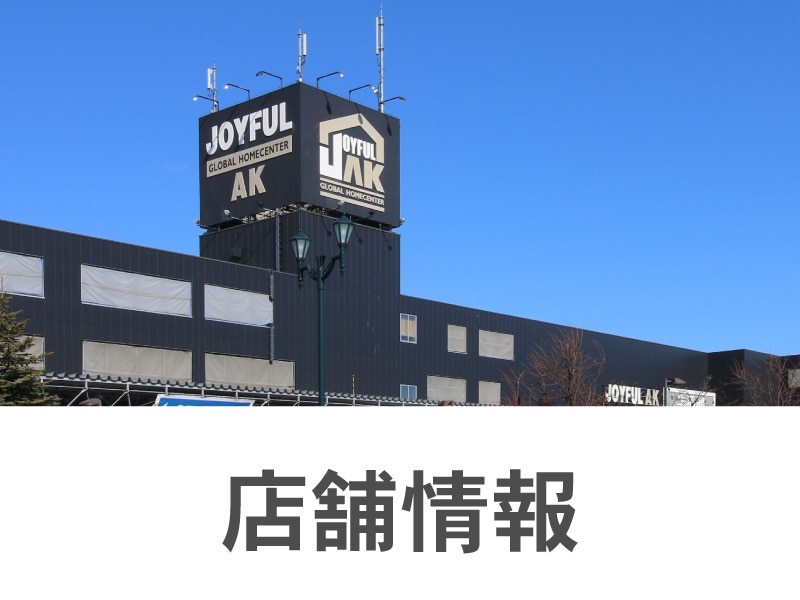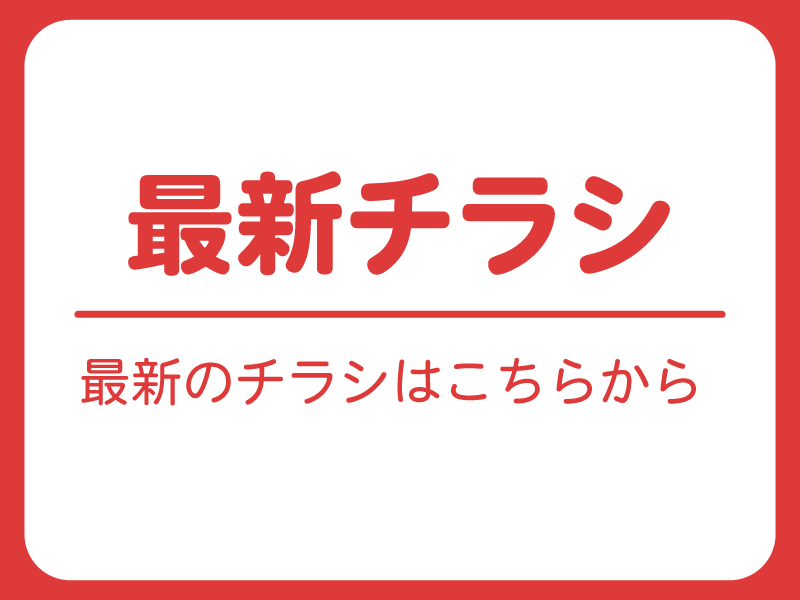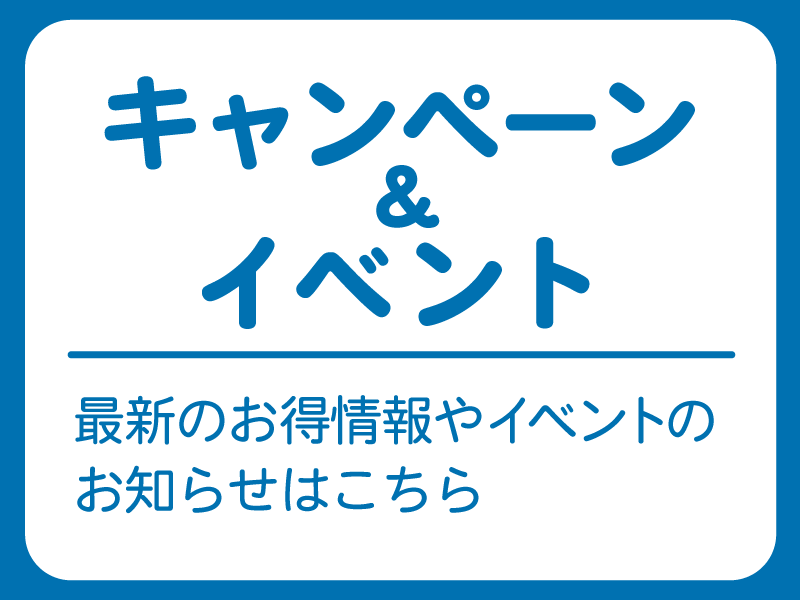仏壇を用意した先のもう一歩。お供えものの決まりって?
そもそも「お供え」とはどういうことなのか
「仏壇を用意したけれど、なんだか殺風景」と、思われているなら、お供えをしませんか? 仏壇に食べ物や仏具を飾っているのが一般的ですが、これがお供えです。お供えは、敬うべき方をもてなすための品であり、仏さまと故人の両者に対して敬意や感謝の気持ちを伝える手段と考えると分かりやすいでしょう。
仏壇に供えるものとは?

「五供(ごくう)」と呼ばれる5つのお供え物を揃えるのが一般的です。
香
線香やお香など、香りのするものを仏壇に向かう際に焚くことで、身や部屋を浄化するといわれています。線香だけでなく、香炉や線香立てがあると便利です。
花
仏花だけでなく、故人が生前好きだった花を飾るのも喜ばれるでしょう。ただし、毒や棘のあるものは向きません。生花の管理が大変なら造花を使用するのもおすすめです。
灯燭
線香に火をつける際や、供物を供える際に灯すローソクです。悩みや煩悩を祓う効果があり、気持ちを引き締めるといわれており、供養する側にも大きな意味があります。灯燭立てを用意しておきましょう。
浄水
汲みたてのお水や一番茶など、水分を毎日供えます。仏具の中には専用の茶湯器もありますが、故人が愛用していた湯呑やぐい呑を使う方もみられます。
飲食
ご飯を炊いたら、一膳目は自分たちが食べる前に仏飯器によそって仏壇にお供えします。お供えしたものは長く置かず、手を合わせたら下げて頂くので、多めに炊く必要はありません。
もてなす心が現れたお供えを

浄水は浄土真宗では供えないなど、お供え物の制限や伝統には、宗派や地域差によって差があります。そのため、まずは地域の年配者や親戚に聞いてみるのもいいでしょう。ですが、時代とともに変化することもあり、ある程度型を気にすることも必要ですが、「お供え」とはもてなし。心から故人と向き合える環境であることが大切なのではないでしょうか?